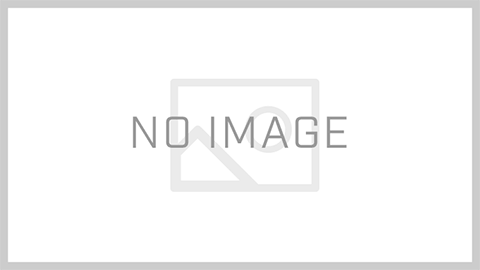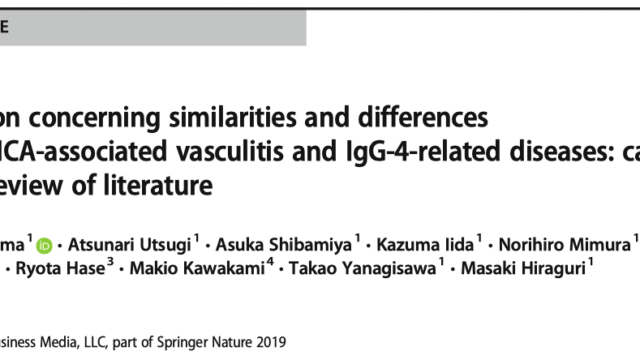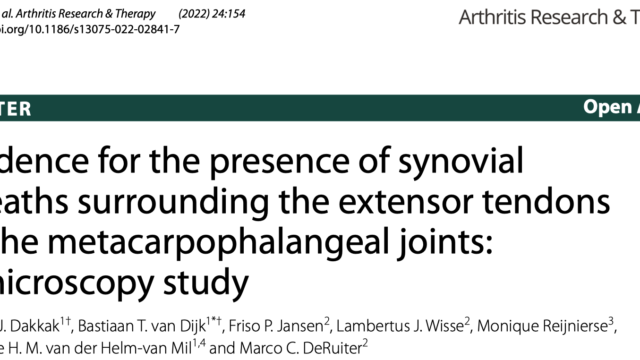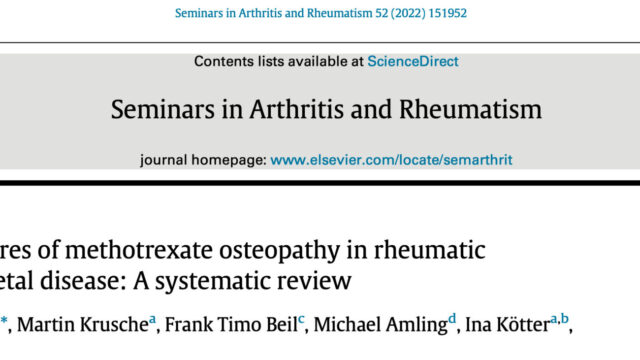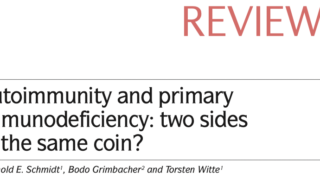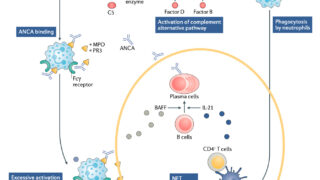Anti–Double-Stranded DNA Antibodies Recognize DNA Presented on HLA Class II Molecules of Systemic Lupus Erythematosus Risk Alleles. Arthritis & Rheumatology Vol. 74, No. 1, January 2022, pp 105–111
Anti–Double-Stranded DNA Antibodies Recognize DNA Presented on HLA Class II Molecules of Systemic Lupus Erythematosus Risk Alleles. Arthritis & Rheumatology Vol. 74, No. 1, January 2022, pp 105–111
【INTRODUCTION】
-
Systemic lupus erythematosus (SLE) 全身性エリテマトーデスは、B細胞のhyperactivity活動亢進とDNAや様々な抗原に対する自己抗体の産生を特徴とする自己免疫疾患である
-
抗DNA抗体産生の正確なメカニズムは未だ不明だが、特定の分子と結合したDNAが抗DNA抗体産生に関与していると考えられている Nat Rev Rheumatol 2015;11:530–40.
-
特定のHLAクラスII対立遺伝子は、SLEの感受性と関連している Rheumatology (Oxford) 2013;52:1172–82.
-
HLAクラスII分子がmisfoldedの細胞内タンパク質をpeptidesまで代謝せずに細胞表面に輸送する
-
misfoldedタンパク質は、自己免疫疾患において、自己抗体の特異的なターゲットであることが分かっている Arthritis Rheumatol 2017;69:2069–80.
-
非免疫細胞がインターフェロン-γ(IFNγ)のようなある種のサイトカインに炎症組織でさらされると、HLAクラスIIの発現が誘導される Nat Rev Immunol 2014;14:719–30.
-
これは、aberrantly異常にHLAクラスII分子の発現によって、細胞表面で発現しているmisfoldedタンパク質が誘導され、自己免疫疾患の病態に関与している可能性を示唆している Arthritis Rheumatol 2017;69:2069–80
-
血中IFNγ濃度の上昇や腎臓におけるHLA class IIの発現量の増加がループス腎炎において観察されている
-
活動性のSLE患者では、アポトーシス細胞のクリアランスが低下し、circulating DNA levels 循環DNAレベルが上昇している Nat Rev Rheumatol 2015;11:530–40.
仮説:
-
DNAもHLAクラスII分子と関連しているのではないか
-
HLAクラスII分子と結合したDNAはanti-DNA B cell receptors 抗DNA B細胞受容体(BCR)を発現しているB細胞の活性化に関与しているのではないか
【MATERIALS AND METHODS】
細胞 Cells
-
HEK 293T cellsおよびB16-F10 cellsは、定期的にマイコプラズマの混入の有無を検査した
-
B16-F10 cellsに関しては、major histocompatibility complex (MHC) class II transcription activator (CIITA)主要組織適合性複合体クラスII転写活性化因子 を欠損しているものをpX330 clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR)/ CRISPR-associated protein 9 (Cas9) vectorを用いて作製した
患者のHLAジェノタイピングデータ Patient HLA genotyping data
-
HLA-DRB1対立遺伝子とSLEリスクとの関連についてのオッズ比は、HLA-DRB1のhigh-resolution genotyping高解像度ジェノタイピングから得られた
-
HLA genotypingヒトゲノムDNAの使用は、理化学研究所の倫理委員会によって承認された
プラスミド Plasmids
-
異なるMHCクラスIIアレルの相補DNAを末梢血単核細胞(3H Biomedical)とIgα(NM_007655.3)およびIgβ(NM_008339.2)からクローニングした
-
共有結合したトランスフェリン受容体(RVEYHFLSPYVSPKESP)およびSP3ペプチド(AILEFRAMAQFSRKTD)を含んでいるHLADRB1*01:01およびHLA-DRB1*15:01は以前の知見と同じように調製した Arthritis Rheumatol 2017;69:2069–80.
DNA
-
ゲノムDNAは、マウス肝臓から調製した
-
Biotinylated oligonucleotides(5ʹ-biotinATGCACTCTGCAGGCTTCTC-3ʹ)はFasmac、phosphorothioate oligonucleotidesはGene Design(日本、茨城)でそれぞれ合成された
Analysis of autoantibody binding to the DNA/MHC class II complex DNA/MHC class II 複合体へ結合する自己抗体の解析
-
HLA-DRα, HLA-DRβ, 緑色蛍光タンパク質 (GFP) をコードする発現ベクターを Polyethylenimine Max を用いて細胞内に共導入した
-
24時間後、培地をDNAまたはDNase I(0.1 mg/ml;Roche)を含む培地に置き換えてし、その後37℃で24時間培養した
-
B16-F10 cellsは、DNAとIFNγ(3.16×10 4 units/ml)と共培養した
-
HLA-DRは、抗HLA class IIモノクローナル抗体(mAb)L243(ATCC)、次いでallophycocyanin (APC)標識された抗マウスIgG抗体で検出した
-
B16-F10 cells は APC結合抗マウスI-A b (M5) (BioLegend)で染色した
-
DNAはヒト抗DNA mAb (71F12) で検出し、続いてAPC標識抗ヒトIgG-Fc抗体で検出した
-
ビオチン化DNAは、APC-conjugated streptavidinで検出した。
-
Histone H3は、抗ヒストンH3抗体ab5103(Abcam)、次いでAPC標識抗ウサギIgG抗体を用いて検出した
-
染色した細胞は、FACSCaliburを用いて解析した
-
細胞上の各分子の染色の平均蛍光強度(MFI)は、GFP単独で遺伝子導入した細胞から得られたMFI値を差し引くことによって算出した
沈殿とイムノブロット Precipitation and immunoblotting
-
HLA-DRαおよびHLA-DRβをHEK 293T cellsに共導入し、20merのビオチン化リン酸化オリゴヌクレオチドを37℃で24時間培養した
-
streptavidin–Sepharoseで沈殿させた後、cell lysatesからの溶出物をドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動にかけ、membranesにブロッティングした
-
この膜を抗HLA-DRα抗体FL-254、次にanti-rabbit IgG antibodyと共培養した
抗DNA BCRレポーターアッセイ Anti-DNA BCR reporter assay
-
ヒトIgM(71F12)重鎖、軽鎖、Igα、およびIgβを、pMXs retroviral expression vectorおよびPlat-E retroviral packaging cellsを用いて、NFAT-GFP reporter geneとともにmouse T cell hybridomasに安定的に遺伝子導入した
-
DNA に対するReporter cell reactivityは、10 μg/ml streptavidin-coated plateにimmobilized固定化したビオチン化 DNA (0.2-2 ng/ml) で刺激して確認し、1 × 10 4 B16-F10 細胞に DNA と IFNγを共培養し、96穴プレートで 48 時間培養を行った
-
CD45陽性細胞におけるGFP発現はフローサイトメトリーで解析した
-
supernatants上清中のIL-2の産生は、抗IL-2 mAbおよびビオチン化抗マウスIL-2 mAbを用いて測定した
Statistical analysis
-
ピアソンの積率相関係数とスチューデントのt検定
【結果】
-
DNAとHLAクラスII分子との結合
-
DNAが細胞表面のHLAクラスII分子と結合しうるかどうかを、SLE患者由来のDNA特異的ヒトmAb 71F12を用いて調べた

-
次に、IFNγ刺激によりMHCクラスIIの発現が誘導されるネズミの細胞株であるB16-F10 cellsを用いて、
-
DNAが内因性に発現するMHCクラスII分子上に提示されるかどうかを解析した

-
今度は、DNAが細胞表面のHLAクラスII分子に直接結合するか、あるいはendocytosisエンドサイトーシスされたDNAが、ペプチド抗原と同様にHLAクラスII分子上に提示されるかどうかを調べた

-
さらに、ビオチン化オリゴヌクレオチドを用いて、HLAクラスII分子がDNAのendocytosisエンドサイトーシスに関与しているかどうかを検討した


-
これらの結果は、DNAは細胞表面のHLAクラスII分子には直接結合せず、endocytosisされたDNAはHLAクラスII分子上に提示されることを示唆している
-
また、HLAクラスII分子自身はDNAのendocytosisに影響を与えない
-
細胞DNAは生理的条件下ではヒストンなどの特定のDNA結合タンパク質と複合体を形成する
-
そのため、sonicated cells からの非精製DNAがHLAクラスII分子上にも提示されるかどうかを分析した

【DNAとの結合におけるHLAクラスII分子のペプチド結合溝の関与Involvement of the peptide-binding groove of HLA class II molecules in the binding of DNA】
-
DNAがHLAクラスII分子に直接結合するかどうかを検討した
-
Mock transfectants や HLA–DR transfectantsをオチン化オリゴヌクレオチドと共培養した

A:
HLA-DRはオリゴヌクレオチドの沈殿においてはっきりと検出されたが、コントロールの沈殿には検出されなかった
これはDNAとHLA-DR分子が物理的に結びついていることを示唆
次に、HLAクラスII分子のペプチド結合溝が、DNAとの結合に関与しているかどうかを解析した
B, C:
HLA-DR15分子に、HLA-DR15と親和性の高いSP3ペプチド(SP3-pep-HLA-DRB1*15:01)を共有結合させたものを調べたHLA-DRの発現量は野生型HLA-DR15、SP3ペプチドを付加したHLA-DR15ともに同じ
一方でペプチド存在下ではHLA-DR15発現細胞へのDNA結合が減少した
D,E :
transferrin receptor peptideを共有結合させたHLA-DR1分子においても同様の結果であった
-
これらの結果は、HLAクラスII分子のペプチド結合溝がDNAの提示に関与していることを示している
F, G :
HLAクラスII分子とDNAの結合にヒストンが関与しているかどうかを調べた
HLA-DR15発現細胞の細胞表面にはDNAが検出されたが、細胞表面にはヒストンが検出されなかった
一方、細胞内にはヒストンが十分に検出され、これはDNAはヒストンとは独立してHLAクラスII分子に結合していることが示唆している
【HLADRへのDNAの結合と各HLA-DR対立遺伝子がもたらすSLE感受性の有意な相関 Significant correlation of the binding of DNA to HLADR with the SLE susceptibility conferred by each HLA–DR allele】
-
HLA-DRへのDNAの結合が、それぞれのHLAクラスII対立遺伝子によってもたらされるSLEのリスクと関連しているかどうかを調べるために、異なる対立遺伝子を持つHLA-DRと結合する細胞表面DNAの量を分析した

-
各HLA-DR対立遺伝子へのDNAの結合と、その対立遺伝子とSLEの関連性に関するオッズ比には、有意な正の相関が認められた

【DNA/MHC class II complexを発現する細胞による、抗DNA BCRを発現するreporter cellsの活性化 Activation of reporter cells expressing anti-DNA BCR by cells expressing the DNA/MHC class II complex】
-
MHCクラスII分子に結合したDNAが、抗DNA BCRを発現するB細胞の活性化に関与しているかどうかを解析
-
mAb 71F12の可変領域を持つ膜型BCRを作製し、mAb 71F12の可変領域を持つ膜型BCRを作製した。71F12 BCRを、受容体crosslinkingによりGFPとIL-2の両方を発現するNFAT-GFPreporter cellsに遺伝子導入した


-
これらの結果は、抗DNA BCRがMHCクラスII分子と結合したDNAによって活性化されている可能性があることを示唆している
【議論】
-
細胞表面におけるDNAの発現が、MHCクラスII分子との関連を介しておこる
-
HLA-DR対立遺伝子へのDNAの結合親和性は、それぞれのHLA-DR対立遺伝子がもたらすSLEのリスクのオッズ比と有意な相関がある
-
このことは、DNAと複合体を形成しやすいHLA-DR対立遺伝子を持つ人は、DNAと複合体を形成しないHLA-DR対立遺伝子を持つ人よりもSLEになりやすいことを示す
-
HLA-DRB1*13:02は、anti–β2 -glycoprotein I antiphospholipid antibody 抗β2 -糖タンパク質I抗リン脂質抗体を持つアフリカ系アメリカ人のSLEのrisk alleleである Arthritis Rheum 1999;42:268–74.
-
一方で、他の集団ではHLA-DRB1*13:02はSLEに対して保護的である Rheumatology (Oxford) 2013;52:1172–82.
-
今回の研究では、HLA-DRB1*13:02へのDNA結合はわずかであり、HLAクラスII分子に結合したDNAは、anti–β2 -glycoprotein I antiphospholipid antibody 抗β2 -糖タンパク質I抗リン脂質抗体の産生に関与していないことを示唆している
-
DNAがMHCクラスII分子によって提示されるためには、endocytosisによって細胞内に取り込まれる必要がある
-
DNAはDAMPであるため、endocytosisされたDNAは細胞ストレスを誘発する可能性がある
-
実際にSLE患者の好中球では、小胞体ストレスが上昇している
-
小胞体ストレスが抗原提示に及ぼす影響は不明であるが、MHCクラスII分子によるDNA提示を促進する可能性がある
-
-
抗DNA BCRを発現しているGFP reporter cellsは、IFNγに刺激されているB16-F10 cells上のMHCクラスII分子上に提示されたDNAによって活性化されることを実証した
-
樹状細胞は、B16-F10 cells上よりも生理的な役割が活発で、より強力な抗原提示細胞を有する
-
またメモリーB細胞の応答はナイーブB細胞の応答よりはるかに高い
-
従って、DNAを提示する樹状細胞は、SLE患者において抗DNA BCRを発現するメモリーB細胞を効率的に刺激する可能性がある
-
-
-
抗DNA抗体の病態生理的機能は不明だが、DNA/HLAクラスII複合体と結合した抗DNA抗体は、antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity抗体依存性細胞傷害を引き起こし、組織障害を引き起こす可能性がある
-
DNA と HLA class II 分子の複合体は、抗 DNA 抗体を産生するための新規抗原性を示す可能性があるが、DNAとMHCクラスII複合体を発現させたtransfectantsをマウスに免疫しただけでは、抗DNA抗体産生を誘導することはできなかった
-
ゆえにDNA/HLA class II 複合体以外に、ある種の未知の因子が抗DNA産生に必要である可能性がある
-
-
DNA反応性CD4+ T細胞は、抗DNA抗体産生に関与している可能性があるが、DNAを認識するTCRは報告されていない Ann N Y Acad Sci 1995;756:428–31.
-
ゆえにDNA 以外の特定の抗原を認識するbystander T cellsが、抗DNA IgG 産生に関与している可能性がある
-
-
他にも、CD4+ T細胞エピトープを含むある種のペプチドがDNAと結合し、HLAクラスII分子上に提示されたDNA/ペプチド複合体が、CD4+ヘルパーT細胞の活性化を介して抗DNA抗体産生に関与する可能性もある
-
DNA/HLAクラスII複合体がどのように抗DNA抗体産生に関与しうるか、さらなる研究が必要である